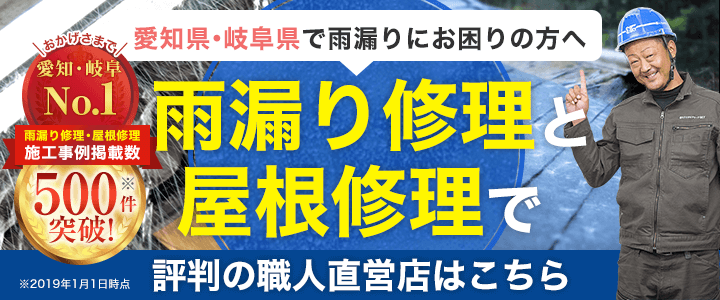雨樋
2019/06/11
わが国の文献に雨といが初登場するのは、平安時代後期に作られた歴史物語「大鏡」の中の〈花山院家造り〉の一節「あわいに“ひ”をかけて涼し」という記述です。この“ひ”は“樋”を意味し、当時の建築様式であった多棟住宅の谷の部分「あわい」に取り付けた「受け樋」であろうと考えられています。当時の「受け樋」は「懸樋(かけひ)」ともいわれ、雨水を排水する役目よりも、むしろ飲料水や生活用水として貴重であった雨水を、屋根から水槽に導く「上水道」の役割を果たしていたようです。
現在のように屋根の雨水を排水するという役割の雨といで、わが国に現存する最古のものは、
奈良時代(733年)に建立された東大寺三月堂の木製といだといわれています。
このといは、厚さ約5cmの板3枚をU字型に組み立てたものです。
雨といは江戸時代まで、神社仏閣を中心に普及してきました。当時の神社仏閣には、すでに飛鳥時代に中国、朝鮮から伝来した瓦が使われ、雨水を処理する雨といが必要だったと考えられます。しかし、一般の住宅は「草ぶき」や「かやぶき」がほとんどで、屋根自体が水分を吸収することや、軒先を作業場として利用する必要から庇(ひさし)を長く張り出して軒を深く取っていたため、雨といの必要がなかったのでしょう。奈良時代前後の雨といは、大きな寺院など特別な建物だけに使われていたためか、当時としてはたいへん貴重な材料が使われている例が少なくありません。なかでも奈良時代(859年)に建立された京都・石清水八幡宮の雨といは、なんと”黄金の雨とい”。古今東西を通じて最高の材料といえるでしょう。この雨といは、1580年の修復に当たって織田信長が秀吉に命じて寄進させたもので、金を主成分に、銀、錫、銅の合金の鋳物で半円形の雨といがつくられ、本殿の「受け樋」として取り付けられています。しかし、この”黄金の雨とい”は撮影禁止となっており、一般に公開されていない幻の雨といです。また、この神社は江戸時代1634年に徳川三代将軍・家光によって修復された際にも、各門と礼堂に銅を使った「箱どい」と呼ばれる角形の雨といが取り付けられています。
江戸時代に入ると商業が盛んになり、江戸、大阪、京都などを中心に人口が集中し、都市が形成されていきます。それに伴って住宅も密集して隣家と軒を接するようになり、隣家の雨水が流れ込む、雨だれが跳ね返って壁を汚す、土台を腐らせる、といったトラブルが起こるようになります。
一方、密集した「かやぶき、板ぶき屋根」の町家は火災に弱く、ひとたび出火すれば次々と類焼して、町中が火の海ということがたびたび起こりました。大火に悩んだ幕府は1720年、防火のために民家の屋根を「瓦ぶき」にするよう奨励しました。
また、商家では財産を火災や盗難から守る土蔵をはじめ、経済力にものをいわせて住宅を豪華にすることで武士階級に対抗したため、瓦屋根でしかも複雑な屋根構造の町家が出現するようになりました。このように瓦ぶき屋根が一般的に普及するようになると、雨水の落下で柱の根元や土台が腐ったり、傷んだりするのを防ぐため、雨といが使われるようになったのです。
当時は、建築物の場合と同様、雨といの材料として一般的に手に入るものとしては、木や竹など自然のものしかありませんでした。とりわけ竹は、奈良時代の「懸樋」の頃から利用されており、節を抜けばパイプ状になる、半分に割れば半円形になるなど、雨といの材料としてはたいへん好都合であったことから、最もよく使われる材料であったと考えられます。
当時の雨といの施工方法は、軒先のたる木に板を削った雨とい受けを打ちつけ、その上に竹製の雨といを乗せていたようです。その他には、板をU字型に打ちつけた「箱とい」や2枚の板をV字型に打ちつけた簡素なものがありました。
文明開化とともに海外との交流が盛んになり、さまざまな外国の文化が流入。洋風の建築技術も紹介されていきます。そのなかには、すでに高度な加工技術による装飾性にすぐれた雨といも当然含まれていたと考えられます。
また、当時「ブリキ屋」と呼ばれる専門職が誕生しています。ブリキ(Brrick)とは薄い鉄板に錫をメッキしたものですが、当時は輸入したレンガの包装材料や石油の容器などに使われており、これらの廃品を加工して、煙突や流し台、半円形の軒とい、そして円筒のたてといなどをつくる職人が出現したのです。これが現在の「板金店」のルーツです。

関連記事
2025/12/15
2025/07/28
2025/04/25
2024/12/02
2024/08/01
2024/04/10
2024/01/25
2024/01/17